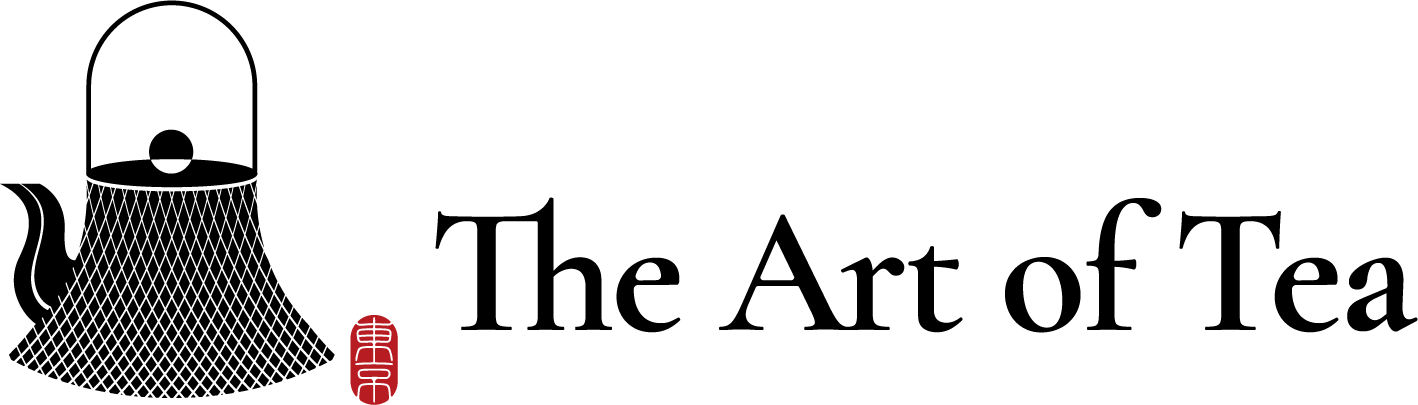安渓肉桂
安渓肉桂は中国福建省泉州市安渓県で作られたお茶です。中国茶の好きな人にとって、「安渓」と聞くと、即時に「鉄観音」を連想されると思います。安渓は鉄観音の有名な産地であり、私も鉄観音の仕入のために何度も足を運んでおります。鉄観音を仕入れるために生産地を訪問していた際、安渓県の大坪村という産地にて肉桂の茶樹が多く栽培されていることを発見し、また、お茶の質が非常に素晴らしいことから仕入を行いました。ただ、以前お付き合いしていた生産者は安渓肉桂の生産をやめてしまい、その後、同質のお茶を探し続けておりました。数年前に質の高いお茶を見つけたのですが、農薬に関して不安がありました。そこで、日本の規準にあった茶園管理に変更して貰い、更に、約400種類の農薬検査を行うことで日本基準を満たしていることが確認できたため、数年ぶりに仕入をすることが出来ました。
仄かにシナモンの香りがすることから肉桂と呼ばれる
肉桂(ニッケイ)はあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、肉桂はシナモン、カシア、ニッキなどの香辛料の原料に共通する、クスノキ科ニッケイ属の植物の名称です。安渓肉桂の「肉桂」はお茶の品種名で、シナモンやニッキのような香りがする特徴がゆえにその様な名称がついております。HOJOで紹介する安渓肉桂はやや強めに焙煎を行っており、やわらかなシナモン風の香りと、甘い栗のような香りが特徴のお茶です。
成長が遅く余韻の強いお茶
肉桂は、他の品種(安渓だと毛蟹、鉄観音、黄金桂、本山など)と比べて芽が出るのが遅い特徴があります。私の経験上、成長の早さはそのままに後味(余韻・コク)と比例関係にあります。例えば、成長が非常に速いことで知られる毛蟹などの品種は余韻が軽い(後味が弱い)点が特徴のお茶です。肉桂の場合、このような品種特性もあり、肉桂は後味が強く、飲みごたえのあるお茶です。
美味しい飲み方
使用する水
身近な水と言うことで、水道水をお薦めいたします。水道水を使用される場合は、消毒用の塩素を取り除くため3~5分沸騰させてください。但し、例え沸騰しても塩素を完全に除去することは出来ません。可能な限り、活性炭フィルター付きの浄水器を用い、水中の塩素を除去してください。そうしないと、お茶の香り成分と塩素が共に反応し合い、本来の香りが楽しめません。また、塩素は微生物を殺菌するためにいれられております。殺すのは健康に害のある微生物だけでなく、私達の腸にすむ善玉菌も同様に殺菌してしまいます。また、細胞レベルでも様々な害が報告されており、アレルギーの原因にも成り得ます。
蒸留水や逆浸透膜水の場合、ミネラルを全く含まないために、お茶の味がフラットになりがちです。出来るだけ水道水等、ミネラル水をご使用ください。
尚、ヤカンに付着した水垢(スケール)は決して除去しないでください。クエン酸洗浄などを行うことで、従来のお茶の味が得られなくなってしまいます。
一端使用される水の種類を決められたら、今後、水の種類を変えないように同じ種類の水を使用し続けてください。水の種類が変わった場合、スケールからミネラルが大量に溶出し、暫く使っていると、お茶の味が劇的にまずくなります。同じ水を使用し続けることが、お茶を美味しくいれるための秘訣です。
茶葉の量
通常、40mlの湯に対し1gの茶葉を用います。つまり、200mlの湯が入る急須の場合、200÷40=5gとなります。同様に300mlの場合8gの茶葉を用いてください。
温度管理は烏龍茶の命
烏龍茶をいれる場合、最も大切なのが湯の温度管理です。
ただ熱いお湯を使えば良いと言うわけではありません。
例え熱い湯を使用しても、いれている過程で冷めてしまったのでは、ぬるま湯を使ってお茶をいれるのと大差がありません。
そこで、以下の2点が重要になります。
茶器の温度を上げる
沸騰している湯を急須に入れてください。
そのまま、10秒間静置してください。これにより、茶器が暖まります。
私達の実験によると、沸騰水を茶器に入れるだけで20℃温度が下がります。
つまり、熱水で暖めているつもりでも、実は80℃になっているだけです。
烏龍茶をより美味しくいれたい場合、特に、高級な烏龍茶の場合、2回この動作を繰り返されることをお勧めいたします。2回熱水を注ぐことで、急須の温度は95℃ぐらいまで上昇します。
茶葉の温度を上げる
折角茶器を温めても、即お茶をいれた場合、茶葉により湯の温度が下がってしまいます。「茶葉ごときでそんな?」と思われるかもしれませんが、茶葉は表面積が非常に大きいため、熱交換率が高く、私達の実験では20℃温度が低下します。つまり、No.1の手順に基づいて、茶器を温めたとしても、再び20℃下がってしまうわけです。
そこで、再び沸騰水を茶葉に注いでください。注ぐときは、勢いよく、出来るだけ低い位置から素早く注ぎ入れます。チョロチョロとのんびり注いだ場合、その過程で温度が下がってしまいます。高い位置から注ぐと、同じく、温度が下がります。湯を注いだら、7-10秒ほど湯につけ、そして素早く、湯を注ぎだしてください。このときにノンビリとしていると、折角のお茶の味が失われてしまいます。かと言って、短すぎると、茶葉が暖まりません。
1と2の動作は非常に重要であり、この2つをマスターするだけで、烏龍茶の味は劇的に変わります。逆に、1と2をやらなかった場合、自分的には100℃でいれているつもりが、実際には60℃でお茶をいれているわけで、今一キレのない味になってしまいます。
お茶をいれる時間は、以下の通りです。
洗茶:7-8秒
1煎目:20-30秒
2煎目以降:10秒
上記の時間だけいれたら、必ずお茶を全て注ぎだしてください。
湯が急須に残った状態で放置しておくと、茶葉は熱水により抽出され続け、2煎目以降非常に味が濃くなってしまい、また、茶葉が酸化してしまいます。
更に、湯を注ぎだしたら、必ず、蓋を外し、茶葉を冷却しましょう。この動作は非常に重要なのですが、意外に知られておりません。冷却することで、酸化を防止し、茶葉を新鮮な状態に保つのです。
茶葉の保存方法
常温にて保管されることをお薦めいたします。
お茶は湿度に弱く、水分を少しでも吸収した場合、即劣化が開始されます。
水分は以下のような状況で意図せず吸収されますのでご注意ください。
- お茶を淹れる際に、近くに置いてあり湯気が触れる
- スプーンなどに水分が付着している
- 湿度の高い日や場所で開封したため
- 冷蔵庫から出した際に、即開封したために、結露が発生
- 冷蔵庫から出して、暫く未開封のまま常温に戻したものの、シールが完全でなく結露が発生
実際、茶葉が劣化する最大の原因は4と5のようです。
冷蔵庫に保管した場合、袋の内部は冷えており、テープなどでしっかりとシールしていても、かなりの率で外気が中に進入し、結露を起こします。茶葉を結露してしまった場合、2-3日で香りが劇的に変化します。
出来る限り、常温で保管し、しっかりと乾燥した部屋でシールをすることで湿度を避けて保管してください。開封したら数ヶ月内に消費してしまうのが理想です。
未開封で真空包装されている商品につきましては、1年以上の保管が可能です。更に熟成を進めたい場合、常温にて、未開封のまま(真空包装のまま)保管してください。尚、購入直後のままの品質を維持されたい方は冷蔵庫にて保管してください。冷蔵庫に保管された場合は、必ず、24時間かけ常温に戻してから開封するようにしてください。半日もおけば大丈夫と思われがちですが、茶葉は大変表面積が大きく、天然の断熱材と言っても過言ではありません。手で触ってみると、既に常温に戻っているように感じられますが、内部は冷えており、十分に温度を常温に戻すには24時間必要です。尚、一端冷蔵庫からだし、開封された後は、常温にて保管してください。秋~春は外気の温度が低いため、常温保存をしても数ヶ月以上美味しい状態を維持することが出来ます。
オプションを選択