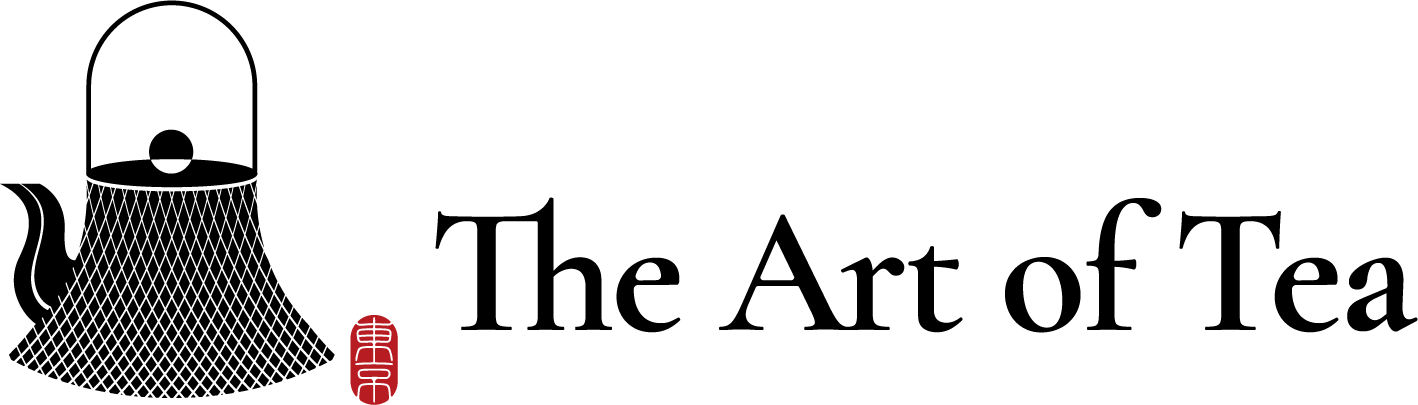都祁在来煎茶
古代日本の中心地との説もある都祁(つげ)
都祁は、奈良県の北東部、大和高原に位置する地名です。かつて、都祁は都祁村でしたが2005年に奈良市に併合されました。 現在も、都祁は地名として残っており、都祁在来煎茶の産地は都祁白石町という地域になります。 
都祁は古代日本史を語る上では非常に興味深い地域です。
この地域には三陵墓古墳群史跡のような前方後円墳をはじめ、白石国津神社・雄神神社・都祁山口神社のような、古代日本と関わりの深い重要な文化遺産が点在しております。都祁における多くの神社は大国主命との関わりが深く、この地域は旧出雲村だったとの説もあります。
古事記では、大国主命が天照大御神(渡来人と思われる)に葦原中津国(日本)を国譲りをしておりますが、その当時の日本の中心地(都)は都祁の辺りだったのかもしれません。
ミネラルが豊富な土壌
都祁在来煎茶の茶園は、国津神社・雄神神社から徒歩圏内の、山の斜面に位置しております。
古代の史跡が多く残る都祁は川などによる浸食を受けにくい土地であり、茶園周辺は粘土質で鉄分を多く含む、褐色森林土壌に覆われております。
都祁在来煎茶が極めて奥行きのある余韻を呈する1つの要因は、褐色森林土壌に含まれる豊富な鉄分ではないかと推察されます。
無農薬無肥料の茶園
都祁在来煎茶は、数十年以上、無肥料無農薬の自然栽培で管理された茶園で作られております。

都祁在来煎茶の茶園と生産者
生産者が保有する複数の茶園ごと、それぞれの品質を評価し、気に入った、単一茶園のお茶のみを仕入れております。

美味しいお茶を求めたとき、その答えは、「健康に育ったお茶」ではないかと私達は考えてます。
健康的な植物の代表は、自然の草木と仮定すると、健康なお茶とは、自然の植物に近い状態で育ったお茶と言えます。
自然の植物は、窒素源を生態系にのみ依存しており、限られた量の窒素で生きております。 肥料(窒素肥料)と共に栽培されお茶は、細胞の窒素濃度が高くなります。その結果、お茶の木は大量の葉緑素を合成し、光合成を活発に行うことで、勢いよく成長しようとします。
肥料を施肥して栽培されたお茶は、成長速度が速く、細胞が肥大化することで、細胞密度が低くなります。 結果、収量が増えるかわりに、後味が薄くなり、奥行きの無い扁平な味になります。
肥料栽培のお茶は、例えるなら、人で言う所のメタボに近い状態と言えます。
化学肥料不使用を売りとしている生産者も散見されますが、私達は、化学肥料でも、有機肥料でも窒素肥料である限り、お茶への影響は同じだと考えております。 尚、同じ肥料でも、草や落ち葉から作られた、炭素性の肥料はお茶や野菜を自然な状態に維持するため問題ありません。
無肥料で栽培すると農薬も不要に
自然の草木を観察すると分かりますが、自然の草木は何も農薬を与えてないにもかかわらず、害虫も付かず、何年も元気に生き続けております。
窒素系の肥料を与えるからこそ、植物(お茶)は昆虫を引き寄せるわけで、それゆえに、農薬が必要となるのです。
例えば、自然の草木であっても、肥料を与えた場合、葉が大きく、色は非常に濃い緑に変化し、同時に虫害を受けるようになります。 無肥料のお茶は、窒素濃度が低いことに加え、ポリフェノールやテルペンなどを多く含みます。これらの生理活性物質は、味香りに寄与する面が大きく、濃厚な味、フルーツや花のような香りを形成します。



無肥料栽培のお茶は、成長が遅いため、活発な光合成を必要としません。この為、葉緑素が少なく、全体に黄緑色をしている点が特徴です。

実生のお茶
都祁在来煎茶は実生のお茶から作られております。 実生とは種から撒かれたお茶のことであり、日本では在来種と呼ばれます。
本来、在来種とはツキノワグマ、ニホンカモシカ、ヤマトイワナなど日本古来の動植物に対して用いる名称です。 お茶は元々、中国から渡来した植物であることから、在来種という名称は本来適切ではありません。とはいえ、日本のお茶業界では実生のお茶の事を在来種と呼ぶため、HOJOでも分かりやすく在来という名称を用いております。
ヤブキタ、オクミドリ、ベニフウキのように、品種名の付くお茶は挿し木によって植えられます。 種をまくと、交配することで雑種が生まれるため、特定の品種を作る為には、挿し木か接ぎ木が必須なのです。
挿し木と比べ、実生のお茶は、根の構造が全く異なります。 以下の写真を見ていただくと違いは一目瞭然です。 
左が挿し木(品種もの)、右が実生(種から栽培) 種から撒かれたお茶の木は、直根と言って、ゴボウのように長い根を形成します。この為、地中のミネラルを吸収しやすく、より、濃い後味のお茶となります。
都祁在来煎茶の味香り
都祁在来煎茶の香りは花系の香りですが、全体に控え目です。 最大の特徴はなんと言っても、非常に長い余韻、濃くて、体の奥に落ちていくような深い後味です。 余韻の長さという点では、HOJOの日本茶の中で最大であり、素材の良さが際立っております。 製茶はやや荒削り感がありますが、素材の良さゆえに、飲みごたえのあるお茶です。
オプションを選択