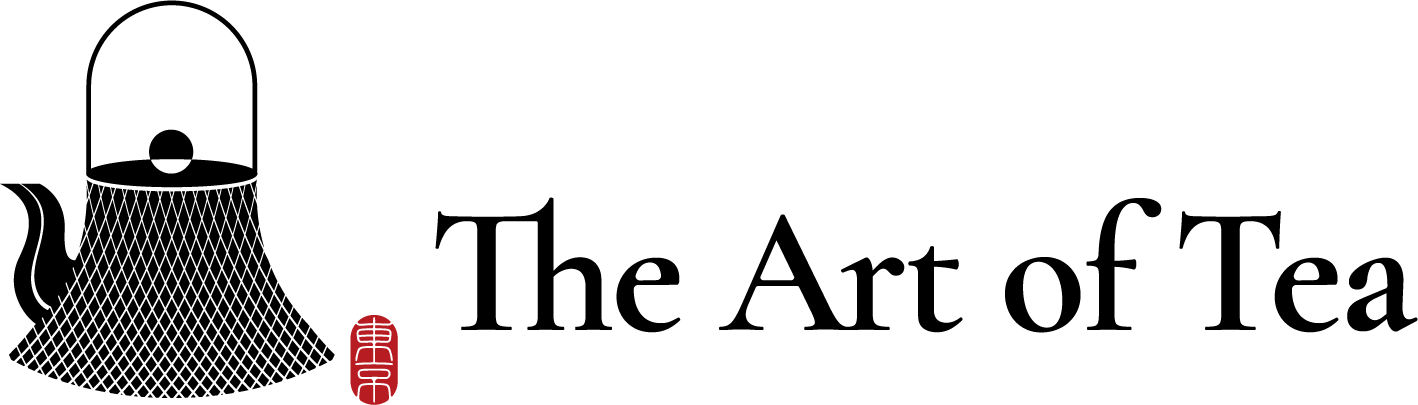野生紅
人里離れた雲南省の山奥に自生する野生のお茶からつくられた紅茶
野生紅は雲南省の山奥に自生する野生茶から作られた力強い紅茶です。 野生茶とは、人間の手が全くかかってない、山の中に自生しているお茶のことです。
蜜のような甘い香りが特徴的で、ボディがとても強く、野生茶だけに強烈に深いコクを併せ持ちます。
ミネラルが豊富に含まれ、血行が良くなることから、飲んだ瞬間に体が温かくなり、瞬時にリラックスすることができます。

2016年産は野生の茶樹の中でも樹齢が非常に高い老木を中心に原料を仕入れることが出来ました。透明感のある、気品のある香りに仕上がっております。
珍しいお茶ですが、非常にリピート率の高い人気商品です。
野生のお茶の木から収穫された茶葉から作られた紅茶です。

野生のお茶の木とは、雲南省に多く見られる樹齢が数百年や千年を超える老木のことではなく、人里離れた山奥に自生している天然のお茶の木を指します。
これまで野生茶を用いたお茶と言えば、プーアル生茶しかありませんでした。野生茶を用いた紅茶は、正直今回初めて見ました。
野生茶で紅茶を作るという発想が面白く、飲む前から仕入れる気満々で試飲に臨みました。

香りは非常に複雑で、ボディがとても強く、野生茶だけに強烈に深いコクを併せ持ちます。このお茶の場合、お茶を淹れるのに用いる水によってお茶の香りが顕著に変化し、相性が良いと、まるで東方美人のような蜜香が感じられます。
私は自宅の井戸水、水道水、マレーシアの水、雲南省の水でそれぞれ試飲を行いましたが、水によっては、ブ−ケ系、フルーツ、木の皮を連想するような力強い香りがする場合もあります。
ミネラルが豊富に含まれ、血行が良くなることから、お茶を飲むと同時に顔が赤くなり、発汗し、お茶酔いに伴いそのご眠気が襲ってきます。
このような理由から、夕方以降の仕事のあとに飲まれる事をお薦めいたします。

野生茶とは
野生紅は中国雲南省臨滄にある、大雪山という山で収穫された野生のお茶です。 野生茶とは、人間の手が全くかかってない、山の中に自生しているお茶のことです。
実際、中国系のプーアル茶を専門に販売している店やサイトには、必ずと言って良いほど、「野生茶」があります。
但し、その99.99%は野生茶ではなく、いわゆる樹齢の高い木から収穫されたお茶ではないでしょうか。
樹齢の高い古樹茶は、少数民族により数百年から1000年間栽培されているお茶であり、「野生」ではありません。
野生茶とは、文字通り山に生えているお茶です。人間の手は全く入っておりません。

山菜のような美味しさ
春になるとタラの芽やコシアブラなどの山菜を食べますが、山菜は美味しいと思われませんか? 栽培することもできる、三つ葉、ワサビ、セリなども、山に生えている物と栽培品では味が全く異なります。
特に強調したいのは甘さです。野生茶は山で収穫した山菜のように、大変甘く、飲んだ後も甘い余韻が喉に残ります。
私は人生の中でこれほど円やかで、甘いお茶を飲んだことがありません。 野生紅はHOJOで販売するお茶の中でも喉越しが非常に強く、飲んだら即お茶酔いします。
飲んだ瞬間に体が温かくなり、瞬時にリラックスすることができます。

山ブドウのような香り
野生茶というと、苦いお茶が多く、どちらかと言うとマニア向けのお茶というのが一般的ですが、野生紅は例外と言えます。
再び山菜で例えますが、山菜でも時々苦い個体、或いはえぐみのある物があるように、野生茶の味も木によって異なります。昨年販売していた哀牢山野生茶はやや苦みがありました。
それに対し、野生紅は全く苦みがありません。飲むと、木のような力強い香りがし、飲み終わると山ブドウのような、乾燥杏のような果実香が仄かに漂います。
また、このお茶は煙のような香りもします。ただ不思議なことに飲む前は香っていた煙のような香りが口に含むと感じられません。
今回は20種類近い異なる産地の野生茶の中から厳選して苦みのないお茶を選び出しました。
子供が喜ぶお茶
我が家では子供もこのお茶が大好きです。
良いお茶には鉄分が多く含まれるために、お茶の性質は人間の生体水や母乳と性質が似ていると言われております。
香りは子供向けとは思えないのですが、実際に野生茶を淹れると、子供達は口々に「味が濃くて美味しい」と言います。
何度もおかわりするのですが、飲み終わる頃には顔が赤くなり、体もとても暖かくなっております。
鉄分が非常に多いお茶ですので、鉄分が不足気味の現代人が飲むと、体が鉄を欲しているために自然に美味しいと感じるのかもしれません
本来非常に高いお茶
通常野生茶は非常に値段が高く、今回訪れた産地でも野生茶はその殆どが5倍くらいの値段でした。
偶々、大雪山の生産者が野生茶を専門としており、直接仕入れることができた事で、非常に安価に仕入れることができました。
野生茶と普通のお茶と何が違う?
野生のお茶は他の植物との熾烈な競争の中で育ちます。 日光が遮られ、薄暗い森の中でお茶の葉は日光を受けようと必死に上に向かって伸びます。
この結果、お茶の木は光が当たる先端にだけ葉を付けます。巨大な木にもかかわらず、少量の茶葉には多量のミネラルが含まれます。
また、剪定も、肥料もない野生の山の中では、お茶の木は極めてゆっくりと生長します。この為、一つ一つの細胞が小さく密になり、まるで採れたての山菜のように濃厚な味わいとなります。
鉄分を多量に含んでいるため、鉄を必要としている人にも良いと言われております。 尚、野生茶の特徴として、新茶でもまるで紅葉をした葉のように褐色系の色をしております。
これは野生茶の特徴の1つで、茶葉に含まれる特異的なミネラルが関係していると考えられております。

上の写真は樹齢数百歳のお茶の木です。一般的な高品質のプーアル生茶はこのような老木から作られます。
但し、これらの老樹は野生茶ではありません。 樹齢が古く、茶葉の品質は非常に高いでしょうが、分類としては「栽培茶」となります。

これは最寄りの村から徒歩数時間の山奥に自生する野生のお茶の木です。
野生のお茶は標高2000m付近に自生しており、樹齢は若い木から1000年にもなる木まで様々です。特徴として、芽が太陽の光を求め上へ上へと延びます。
この為、まるでタラの芽やコシアブラの芽のようにヒョロリとしており、逆に新芽の数が少ないため、とてもしっかりとした芽で、厚みと弾力のある葉をしております。
多種多様な種類の野生茶
日本の殆どのお茶の木は挿し木により育成されます。いわゆる、クローンであり、茶園にあるお茶の木は全て同じ品種と言えます。
野生茶の場合はと言うと、山に自生しているため、種が落ちてそこから芽が生えてきます。つまり、全てのお茶は複雑交配により様々な形質を作り出しております。
同じ山のエリア内でも、葉のサイズ、形状、色は勿論、味香りともにお茶の木ごとに全く異なります。 私が実際に複数の木から芽を摘んで試食したところ、非常に爽やかな味わいお茶や、猛烈に苦いお茶が混在しておりました。
実際にお茶を摘む際には、複数の木から摘みます。ところが異なる木の葉は全て味が異なるため、どのように木を組み合わせるかによって最終的に完成したお茶の味は全く異なります。
基本的に野生茶はどれもコク(喉越し)が強く、香りが非常に濃いのですが、偶然の組み合わせによっては、味が薄く、香りの浅いお茶になる事もあります。
この為、野生茶を選ぶときは非常に苦労します。各バッチ毎に数キロしかなく、それぞれのバッチによって味も香りも全く異なります。
野生茶探索のビデオ
私が野生茶の探索を行った際のビデオです。これを見れば、野生茶がより分かります。
オプションを選択