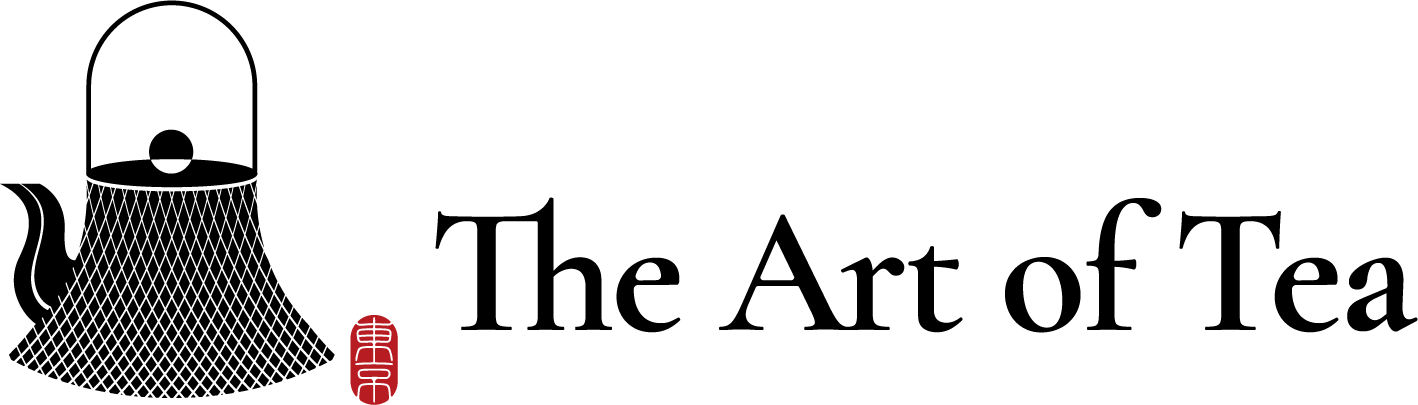宇治焙茶 鷲峰山
旨味=美味しいではありません
現在の日本茶の主流は旨味成分を多く含むお茶です。旨味成分の本体はテアニンと呼ばれるアミノ酸ですが、旨味=美味しいではありません。旨味とは、出汁の素のようなのグルタミン酸ナトリウムに代表される味を指します。
茶葉に含まれるアミノ酸量を増やすためには窒素肥料を施肥する必要があります。窒素肥料が与えられた茶園ではお茶の木は勢い良く成長しますが、反面、カテキンを始めとするポリフェノール・ミネラルの量が少なくなります。
また、テアニンを多く含むお茶は味の深み(コク・余韻)が弱くなるため、お茶の味としてはあっさりとした味になります。
コクの強いお茶がHOJOの日本茶の特徴
HOJOではお茶のコクを重視したお茶選びをしており、テアニンではなく、カテキンとミネラルが豊富に含まれるお茶を選んでおります。ミネラルが多く含まれるお茶とは、自然栽培など無肥料や限定的な肥料により作られたお茶です。
お茶を飲んだときに、喉に残る甘い後味をお楽しみください。
世界の高級茶に通用する非常に深い余韻の焙じ茶をプロデュース
宇治焙茶 鷲峰山は、京都府の和束町にある鷲峰山という山で作られた自然栽培の1番茶を原料とした焙じ茶です。
和束町は、宇治田原町、南山城村、笠置町、月ヶ瀬、朝宮と並び、大昔から良質の宇治茶の産地として知られております。
限りなく深いコクと、何時までも喉に残る甘い余韻はこれまでの焙じ茶の常識が変わります。 世界の銘茶にも匹敵するHOJOの焙じ茶をお楽しみください。
商品詳細
コクがあり香りの余韻が非常に長い焙じ茶をプロデュースしました。自然栽培の1番茶を原料に焙じ茶を特注しました。
飲めば必ず病み付きになります。
上質な中国茶を飲んでいる人にも納得して貰えるレベルの焙じ茶が出来ました。限りなく深いコクと、何時までも喉に残る甘い余韻はこれまでの焙じ茶の常識が変わります。
自画自賛したくなる品質です。
中国のお茶品評会で金賞を取るような、今まで飲んだ事もないような超高品質の焙じ茶を作りたいと思いました。
高い品質のお茶は、味に奥行きがあります。この奥行きゆえに、お茶が軟らかく感じられ、甘い余韻が何時までも感じられます。
この様な味わいを実現するため最も重要なのは原料の選定です。 今回選び出したのは、HOJOで販売している宇治茶 鷲峰山という宇治煎茶です。
このお茶はHOJOのラインアップの中でも特に喉越しが深く、原料の品質がずば抜けて良い事から、この煎茶をそのまま焙じ茶の原料として使う事にしました。
肥料を全く与えずに時間をかけてゆっくりと育てると、茶葉はポリフェノールと鉄分を多く含みます。生の茶葉の香りを嗅いだだけでその違いは一目瞭然です。香りの深さ、味の濃さが全然異なる点はお茶に詳しくない人でも一目瞭然です。
焙じ方にもこだわりました。
原料の煎茶を砂炒りという伝統的な火入れ方法にて焙じました。砂は表面積が大きく、熱が茶葉の隅々まで伝わることで、お茶を均質に焙じることができます。
質の良い烏龍茶のような香ばしく甘い香り
これまで10人近い人に試飲をして貰いましたが、「これは焙じ茶じゃない」というのが、大多数のコメントでした。
本当に焙じ茶の味がしません。高級烏龍茶のような甘い香りと、想像を絶する円やかさ、深い喉越し、そして、持続性のある甘い余韻が特徴です。
淹れたお茶は、キツネ色をしており、焙じ茶と言うより質の高い烏龍茶を飲んでいるような味・香りがします。

艶のある琥珀色をしており、香りを嗅いだ瞬間にこのお茶の実力が想像できます。

淹れ終わった茶殻を触ってみてください。見た目からは想像が出来ないほどに軟らかく弾力があります。
品質の違いを水質で感じてください。
お茶は品質が上がるほど含まれる鉄分の量が増えるため、品質が高いお茶は水の性質その物を変えます。
この鉄分がお茶に溶け出し、水を非常に軟らかく、高い粘度に変えます。この水の性質はやはり同じく鉄分を含む生体水に近く、普通に水を飲むよりも、品質の高いお茶として飲む水は体にとって利用しやすい水です。
宇治焙茶 鷲峰山はその点、水の性質を劇的に変えます。少し飲んだだけで気持ちの良いお茶酔いが感じられます。

焙じ茶と言うよりも烏龍茶のような色合いをしております。

良い品質の焙じ茶ゆえ、小さな茶杯で飲まれるのも良いでしょう。
本商品は宇治煎茶その物を原料として使用しております。茎や番茶を使用して作られる焙じ茶とは異なり、原料自体にコストがかかっております。
更に、焙じ茶を作る場合、追加の火入れを行うために加工中の目減りは避けられません。ゆえに、目減り分がコストに反映する形になり、煎茶よりも多少高い値段になっております。
以下、原料で使用している宇治煎茶 鷲峰山の説明です。
強烈に深い喉越しと、甘い余韻を実現するため、無肥料の自然栽培にこだわりました
鷲峰山は宇治田原町と和束町の間に立地する標高682mの山です。この地は大昔、琵琶湖の底だったことから一帯には豊富な粘土質の赤土が含まれております。
このお茶を仕入れるにあたり、鷲峰山の理想的な環境に加え、原料茶葉は自然栽培のものを選びました。自然栽培とは肥料や農薬を与えず、山に映えている山菜と同じようにじっくりと時間をかけ、丈夫で野性的に育てることです。
現代農業ではお茶の生産には肥料は欠かせません。
しかし、肥料漬けになったお茶は、過度に成長しつづけ、アミノ酸を大量に蓄積する反面、生体調節物質であり、美味しさ、品質の要素である、ポリフェノールやミネラルが非常に薄く、味気ないお茶になります。
世の中一般的の日本茶はアミノ酸過多により、お茶の味が非常に薄いことから、過度に火を入れて香りを引き出すことでお茶の個性を高めておりますが、本来、良いお茶は生の茶葉を食べただけでもその良さに感動する物です。
本などで良いお茶の代名詞のように引用される「テアニンが豊富なお茶」は、言い換えれば、窒素肥料漬けのお茶を意味しており、私の定義では逆に美味しく無いお茶です。
文章だけでは説得力がありませんが、実際に茶園で生葉を食べ比べるとその差は一目瞭然です。今年の新商品を検討した際、どう加工するかを議論する以前の問題として、原料の選定にとことんこだわり抜きました。
良い原料を入手することで、日本茶業界の常識である火入れを殆どしなくても、十分に美味しいお茶を実現しました。
茎を意図的に除去せず、お茶本来の香りを大切にしました。
日本茶の場合、茎は黄色い色をしているため、目立ちます。
現代の製茶の常識では、茎は必ず除去します。茎を除去することで、緑色の綺麗な茶葉に仕上がるため、見た目重視の日本茶業界では茎を除去するのは基本中の基本です。
しかし、HOJOでは茎を敢えて除去しておりません。数々の実験により、茎の存在が非常に重要と気がつきました。 茎にはミネラル分も豊富に含まれており、非常に甘い香りがします。
雁が音のような茎茶を飲まれたことのある人はご存じと思いますが、茎茶は非常に甘いのです!
ただ、1煎分(3-5g)に10本程度です。含まれる茎は果たしこの程度の茎で、飲んだ感じが変わるのでしょうか?
茎の有無を判断するために、手作業(ピンセット)で茎を抜いたお茶と、茎を全く抜かないお茶を飲み比べてみました。
その結果、自分でもビックリするほどに香りが違いました。試飲した人誰に聞いても、茎入りが美味しいという結果でした。
茎を抜いたお茶は、香りがシャープになり、甘いほんわりとした花の香りが劇的に弱まりました。 余談ですが、昔は茶柱が立つと縁起が良いと言いました。
でも、今のお茶は茶柱となる茎が入っておりません。つまり、どうやっても茶柱は立ちません。 昔の人は茎の美味しさを知っており、茎入りでお茶を飲むのが習慣でした。
最近は見た目重視の世の中になり、香りや味を犠牲にしても茎を除去しているのです。
宇治茶では非常に珍しい600mの標高で作られたお茶です。
冬には雪が積もるような高所に茶園が位置しております。この地域は元々琵琶湖の湖底だったこともあり、標高の高い位置は良質の赤土が堆積しており、鉄分を多く含む、深い喉越しのお茶が作られます。 逆に、山の裾になると、川の浸食により削られて出来た地形であるため、砂が多く含まれ、味が薄めのお茶になります。
標高が高いと、昼間はより強い日光を浴びお茶の細胞は活発に光合成を行います。反面、夜は温度が非常に低くなることから、お茶は成長をせず、代わりにポリフェノールとミネラルをたっぷりと蓄えます。
高原野菜は味が濃く美味しいですね。お茶も同じで、高いところで作られたお茶は味が濃く深い喉越しがします。
甘〜い余韻のするお茶を提供するべく完全自然栽培茶園から仕入れ
お茶を飲み込んだ瞬間、普通のお茶とは全く異なる感覚に驚かれることでしょう。
お茶が喉に吸い込まれるようにすうーーーーと奥に入り、まるで胸に落ちてゆくような感覚、そしてそのあとに下の付け根から喉の奥にかけて大変心地よい甘みが感じられます。
これこそ、中国で品評会で入賞するような高級茶特有の感覚です。本来、海外であれば猛烈に高い値段が付く本商品ですが、日本の品質基準がガラパゴス状態になっているお陰で、とても現実的な値段で入手することが出来ました。
良い茶の定義を簡単に言うと、「濃い味」がすることです。濃いとは、コクがあり、喉土の奥でしっかりと味わえる感覚を指します。
安いお茶を茶葉を沢山使って濃く淹れても、渋みと苦みは強くなるものの、「濃く」はなりません。宇治煎茶 鷲峰山は、この定義での濃さが有るお茶です。微量の茶葉でお茶を淹れても、水そのものの味が濃くなるため、深い満足感が感じられます。高級な昆布は水に通すだけでよいと言う話と同じです。
当然、このお茶は、茶葉を一枚味噌汁に入れただけで、まるでシジミの味噌汁のような深い味の味噌汁が出来ます。勿論、シジミの香りはしませんが。
品質の良いお茶は、鼻を摘んで飲んでもその美味しさが分かります。美味しいお茶は味自体が軟らかく深みがあるため、香りが無くても美味しく感じるものです。
茶葉を一枚だけオレンジジュース、ビール、ヨーグルト、コカコーラ、コーヒーに入れてみてください。 とにかく騙されたと思ってやってみてください!常識では考えられないほどに味の激変を体感して頂けるかと思います。
このような不思議な機能は、茶葉の細胞が非常に細かく放出されるミネラル、特に鉄イオンが多いことに起因します。
このお茶には最近の日本茶にありがちなアミノ酸系の香りは全くなく、まるで烏龍茶かと思うほどにスッキリとした、爽やかな香りです。烏龍茶がお好きな方にもピッタリのお茶です。
金色の茶園を求めて
有機栽培の盲点
世の中、有機栽培だから健康に良い、有機栽培だから美味しいという考えが蔓延しております。
確かに、有機栽培は農薬の点では安心ですが、だからといって「美味しい」と「体に良い」とは全く関係ありません。
本来美味しい野菜、果物、お茶を作り上げようと思った場合、植物に時間をかけて成長させ、高い細胞密度の葉を作り上げることで、ポリフェノールとミネラルが豊富に含まれ、味わい深く、コクのある甘みを作り出すことが大切です。
私も多くの有機栽培茶を飲んだことがありますが、多くは言われなければ有機と分からないほど、普通のお茶と大差のない品質でした。
それには、使用する肥料とお茶の育て方が大きく関係しております。有機肥料でも、堆肥のような窒素肥料を与えた場合、結果的に植物が受ける影響は、硝酸塩のような化学肥料を与えるのと同じです。
窒素が与えられると、植物は勢い良く成長します。窒素が入ることで成長のスイッチが入るためです。
勢い良く生長している植物ですが、実は細胞自体が大きく成長する事で大きくなっております。 成長過程にある茶葉は、ポリフェノールを作らないため、それに伴いミネラル分も少ないお茶になります。
自身の成長のために必要な細胞壁の合成などに忙しく、ポリフェノールの合成をしている暇がないのでしょう。
大きな細胞から成る茶葉は、折れやすく、粉が出やすくなります。
私の実家はリンゴ農家ですが、窒素肥料を与えると、リンゴの葉は深い緑色になり、葉のサイズも肥大し、リンゴも大きくなります。
但し、リンゴを食べると一目瞭然。味に濃さが無く、水っぽくて美味しくありません。 私は有機・無機に関係無く、お茶を自然の山野草に近い形で、時間をかけてゆっくりとお茶を育て上げることが重要だと考えております。
厳しい環境下で時間をかけて育ったお茶は、そのお茶の苦労が品質として感じられるものです。

動物の堆肥の脇にあるお茶の木。お茶の木とは思えないほどの巨大で濃い緑色の葉が付いている。このようなお茶の木から採れたお茶は味も薄く、喉越しが殆ど無いお茶になる。
深刈り
お茶の木は深く刈れば刈るほど、翌年には勢い良く茶葉を出します。
「勢い良く」とは、とどのつまり茶葉を構成する細胞が大きくなり、ミネラルの薄いお茶になる事を意味します。
日本茶に限らず、刈り込まれたお茶は量産向き、質を求めるお茶は殆ど刈らずに時間をかけてゆっくりと成長させるのが一般的です。
上記2つは静岡や鹿児島のような有名なお茶生産地ではごく当たり前に行われている取り組みです。 窒素を与え、深刈りをすることで、成長を早め、茶葉のサイズを大きくし、生産量を増やします。
品質が高い=生産量が少なく稀少というのが普通だと思いませんか? 生産量が多くて、品質も高くて、というのは余りに都合の良い話です。
繰り返しになりますが、高原野菜にしても、美味しいリンゴにしても、高級なメロンにしても、美味しさを求めた場合、ゆっくりと時間をかけて成長させること、それにより生産量は落ちる物の、野菜や果物を構成する細胞数は高密度になり、味の濃い食品が出来ます。
これは野菜に限った事ではなく、短期間で成長する養殖の魚と時間をかけてゆっくりと成長する天然の魚を比べても同様の事が言えます。

刈り込まれた茶葉は若い枝を勢い良く生み出し、大きく緑色の茶葉を大量に生産する。
飲めば飲むほど眠くなるお茶
宇治煎茶 鷲峰山に関してはその問題はありません。むしろその逆です。深い眠りを求めている人に最適なお茶です。
ミネラルの多いお茶、つまり、海外の御茶市場で言う所の「高級茶」を飲むと、体がポカポカと暖かくなり、逆に眠たくなります。
お茶にはカフェインが含まれており、飲み過ぎると眠れなくなると言うのは一般的に知られております。但し、品質が上がると、ミネラルの量が増え、その結果血行が改善されることから、むしろ眠くなります。
宇治煎茶 鷲峰山の場合、ミネラルが豊富に含まれるために、軽いお茶酔いをする場合もあり、高級なブランデー・ウイスキー・ワインを飲んだときのように、内面からリラックスします。
これは精神論的な話ではなく、飲み続けると、顔が赤くなり、ふんわり・ほんわかとした気分になってきます。
日本の法律では効能を明記することが許されてないために、詳細は記載できませんが、血行をよくする食品は、リラックス効果に加え、おつうじや、快眠などに寄与します。
実際に飲むことで、体感してみてください。
鷲峰山について
宇治茶 鷲峰山は、京都府の和束町にある鷲峰山という山で作られたお茶です。
和束町は、宇治田原町、南山城村、笠置町、月ヶ瀬、朝宮と並び、大昔から良質の宇治茶の産地として知られております。
元々、琵琶湖の湖底だった土地が隆起し、その後、名張川の浸食により月ヶ瀬特有の河岸段丘が形成されました。
琵琶湖の湖底だったことが関係してか、これらの地域にはきめの細かい極めて良質な赤土があります。
但し、名張川流域であればどこの地域にも赤土があるわけではなく、浸食されていない山の頂上付近に位置する茶園にのみこの土があります。
逆に、河川による浸食で出来た土地の場合、砂が多く含まれ、喉越しのない一般的な日本茶が出来ます。

鷲峰山周辺:この地域は非常に鉄分が豊富な粘土質の赤土で覆われている。

宇治茶の里:山と谷が織りなす独特の環境が、昼夜の温度差を作り出し、良質のお茶を育てる。

貴重な在来種の煎茶から作られたお茶です。
宇治煎茶 鷲峰山は、在来種というお茶から作られております。
在来種とはその昔から日本にある固有種・原生種という意味にとられがちですが、正確には中国から伝承した昔ながらのお茶の特徴を持つお茶のことです。
在来種は野生種に近いことから、藪北などの品種と比べると、根の張りが強く、同じ樹齢の他品種と比べると、根の全長が長くなります。
このため、一般的に品種と比べると、よりミネラルの吸収能が高く、味香りに厚みがあるお茶が出来ます。(味の厚みとは、苦さや渋さのことではなく、味の豊かさ、つまり、余韻の深さを指します。)
在来種と呼ばれる品種は、種から作られたお茶であるため、複雑交配により、同じ茶園でもAからZまでの様々な葉の形、サイズ、色、香り、味が見られます。
中国でも高品質なお茶になるとその多くは在来種から作られており、一般に混合種という呼ばれ方をします。かの有名な龍井茶なども高級品になると混合種から作られます。
以下のビデオは月ヶ瀬のお茶作りを紹介したビデオです。
月ヶ瀬も和束町と同じくもと琵琶湖の湖底だった土地で、土質や生育環境は全く同じです。
このお茶の作り方はお茶の先端だけを軽く剪定することで、一つ一つの枝を爪楊枝のように細くし、お茶が肥料を吸わないように管理しております。 このようにお茶を作り込むことで、黄色の茶葉が生まれます。
オプションを選択