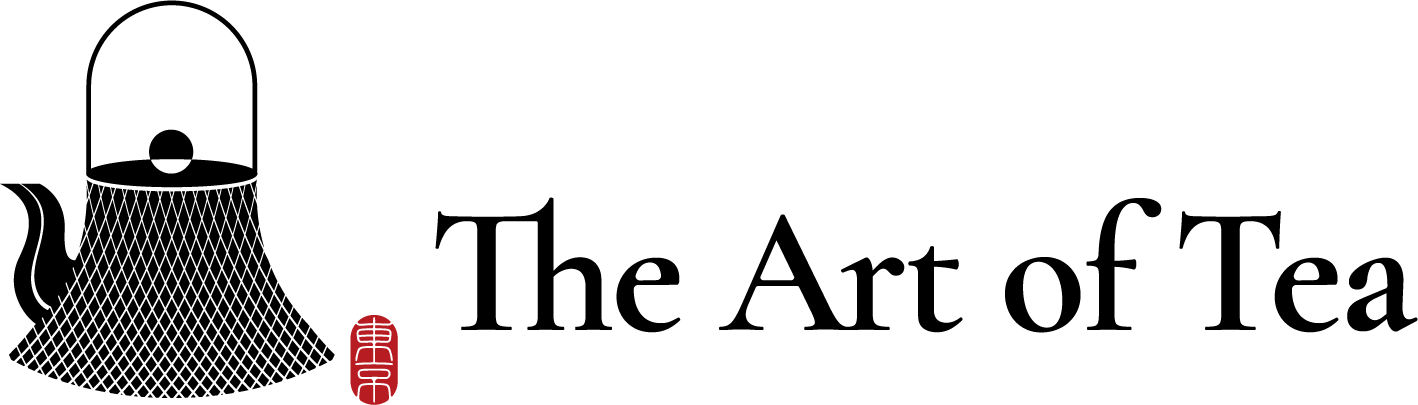木柵鉄観音
伝統製法を今に伝えるお茶
木柵鉄観音は、既に中国では消滅してしまった300年前の安渓鉄観音の香りを今に伝える非常に貴重なお茶です。
時間をかけてじっくりと焙られた茶葉からは乾燥フルーツのような甘い香りと、渋みのない優しい飲み心地が特徴です。
水色は琥珀色をしており、食事やデザートとも大変相性の良いお茶です。
商品詳細
鉄観音と言えば中国を代表する烏龍茶の1つであり、福建省の安渓が産地です。
安渓では16世紀頃までは烏龍茶は作られておらず、烏龍茶の製茶技術は武夷烏龍から伝わったと記録されております。
武夷烏龍の特徴は、長時間にわたる火入れが行われることです。この為、安渓の鉄観音も300年前は火入れが重点的に行われておりました。
武夷烏龍の作り方を踏襲して開発された安渓鉄観音ですが、近代になり独自の進化を遂げました。
蘭の花のような、フルーツのような香りを追求した結果、今では緑茶のように緑色をしたお茶へと進化しました。
一方、台湾の鉄観音は300年前、安渓からの技術導入により発達しました。当時主流だったのは伝統的な重火の鉄観音でした。
台湾に伝わった鉄観音は、ガラパゴス状態となり300年前の作り方が今日まで継承されております。
この為、台湾の木柵鉄管音は昔の鉄観音の製法を今に伝える貴重なお茶と言えます。
木柵鉄観音の水色は琥珀色をしており、乾燥フルーツのような甘い香りと口の中に広がるふくよかな甘い余韻が特徴です。
木柵鉄観音の歴史
木柵鉄管音は台湾の北部、台北市の文山区を起源としております。記録によると、台湾の北部で最初にお茶が植えられたのは今から300年前に遡ります。
清の時代、1796年から1820年の頃、お茶商人の柯朝(Ke Chao)と言う名の福建省武夷山出身の人物がお茶の木を台湾へ持参し台湾北部の文山地区へ植えたとされております。
文山地区はお茶の産地として有名なだけでなく、台湾茶の誕生の地でもあります。更に、今から200年ほど前、鉄観音種のお茶が福建省安渓から持参され、文山地区の木柵という土地に植えられました。
鉄観音種のお茶は最初樟湖山に植えられたそうですが、その後张一家の2兄弟张乃妙( Zhang Nei Miao)と张乃乾(Zhang Nei Qian)が大量の鉄観音種を安渓から持ち帰り、木柵にて大規模生産を始めたとされております。

木柵エリアから見た台北市内

木柵エリアの茶園


オプションを選択